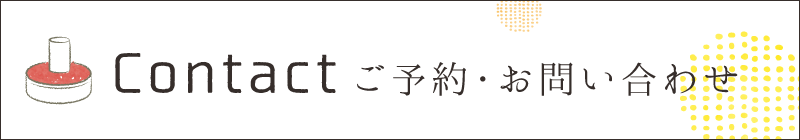5月病〜5つの感情「5志」を考える〜
投稿日:2022年05月13日

こんにちは!
はりきゅうPOKKEの佐藤です。
いつもありがとうございます。
ジメジメしてきたこの頃。
暖かくなったり寒くなったり、朝晩の冷え込みから体調がイマイチ・・・という方は多いかもしれません。
自然界の環境の変化が大きい時(季節の変わり目など)、
人間の体も対応しようと頑張っています。
体はいつもより頑張るので、ちょっと疲れるしいつも通りにはいかないです。
そしてメンタルにも影響が出てくるのは自然なことです。
だから、今「どんよりしてます」という方には、
「季節のせいにしときましょう!ワハハ!」と話したりもします。
また、スッキリしたお天気の日には元気になります。
そう簡単にはいかないこともあるけれど・・・、
「大丈夫」と言いたい^^
東洋医学では、いろいろなことを「陰」と「陽」に分けたり、
5つに分類して考えます。
今回はその「5つ」について。五行論と言います。
東洋医学的に臓器を5つに分けたものが、
五臓
肝・心・脾・肺・腎
肝臓、心臓などの臓器というより(それももちろんですが)、その働きを意味します。
感情も5つに分けられます。
五志
怒る・喜ぶ・思う・憂う・恐る
これがバランスを崩すと、それぞれのカテゴリーと同じ臓腑にも影響があると考えます。
怒は肝を傷る
喜は心を傷る
思は脾を傷る
憂は肺を傷る
恐は腎を傷る
女性にとって、肝・脾・腎は月経と関わりが深いので特に影響を受けやすいです。(だから生理前や生理中にイライラしたりどんよりしやすい・・・栄養とったりお灸で補いましょ^^)
ジメジメ時期には「脾」が影響を受けやすくなります。
「脾」は胃腸の働きと関連が深いため、食べすぎたり味の濃いものや甘いものの食べ過ぎによってバランスを崩します。(便秘や腹痛、お腹が緩くなったり)
ついでに、「脾」は「思」と関わりが深いため、
胃腸の働きが悪くなると思い悩みやすくなったり。
逆に、思い悩むことが多いと、胃腸の不調につながる。
と、どちらからも影響を受けて変化が起こると考えられます。
そんなことを知っているだけでも、少し楽になるんじゃないかなと思います。
4月(春)に、新しい環境や様々な変化があり、それを乗り越え、GW、少し気が緩む・・・。
そこへ5月6月、ジメジメした季節がやってくると、ますます影響を受けやすいわけで。
ここは「ちょっと休憩」という感じで、いつもよりゆっくり過ごすのがおすすめです。
体を程よく動かすのも、停滞する気持ちが動くきっかけにもなります。
ストレッチやヨガで気持ちよく伸ばしましょう^^
お灸してから行うと、よく伸びます。
ぜひお試しくださいませ!
お読みいただきありがとうございました^^