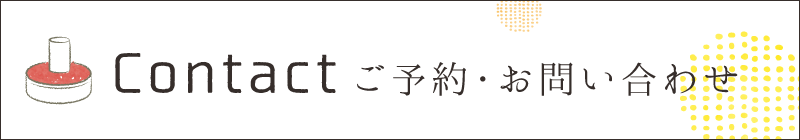東洋医学体の仕組み「五臓六腑」
投稿日:2023年02月22日

こんにちは!
はりきゅうPOKKEの佐藤です。
いつもありがとうございます。
先日、目に何か入り角膜に傷がつき、しばらくメガネでしたが、1週間後に眼科で確認してもらうと綺麗に治っていて、無事にコンタクトを装着できた佐藤です。メガネが苦手なので(目には優しいけど)、やっと快適になりました。
コンタクトを適用期間以上につけたりする方も結構いるようですが、皆様、目は大切に。。。本当に痛かったです。
さて、今回はシリーズで書いていきたいと思います。
知っていると便利な東洋医学的な考え方「五臓六腑」についてご紹介します。
五臓六腑とは聞いたことがあると思います。
2000年以上前から続く東洋医学・中医学的な内臓の表し方です。
五臓・・・心、肺、肝、脾、腎
六腑・・・胃、小腸、大腸、胆嚢、膀胱、三焦(上焦・中焦・下焦)
五臓と違い六腑は入口出口のある袋状のもので、口から入り胃や腸で消化して肛門から出る一つの管=体表と繋がっているところになります。ちなみにそこにつながる「皮膚」は人体最大の臓器とも言われます。
*三焦は水分に関わるためリンパの働きに近いとも言われます。
西洋医学的な臓器そのものの機能だけではなく、もう少し広めに捉えそれぞれの働きを指します。
また、三焦以外は五臓と六腑それぞれ下記のセットで考えます。
・肝と胆
・心と小腸
・脾と胃
・肺と大腸
・腎と膀胱
意外な組み合わせもあると思うかもしれませんが、人の体を診させていただくと、本当に繋がっている、と実感することが多いです。
また、肝は「陰」、胆は「陽」というように、陰(五臓)と陽(六腑)の組み合わせでもあります。
東洋医学、面白い^^
次は、その一つ一つについて書いていきたいと思います。