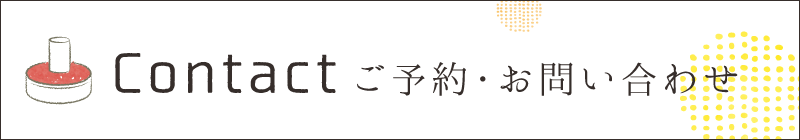「五臓六腑」「肝・胆」
投稿日:2023年02月27日
 こんにちは!
こんにちは!
いつもありがとうございます。
今日は前回の続きです。
五臓六腑の「肝」と「胆」について。
肝・心・脾・肺・腎と、
胆・小腸・胃・大腸・膀胱
のそれぞれの5つが陰と陽で対になっています。
(三焦についてはまた別でご紹介します)
東洋医学的な順番がありますのでその順にご紹介します。
「肝・胆」
のびのびタイプ・不調になるとイライラしやすい
肝(肝と胆ですがわかりやすく「肝」と表します)に関係するもの。
木・春・風・目・筋・酸・涙・怒・青
木 5行の一つである木火土金水の「木」であり、
春 春に影響を受けやすい(不調が現れやすい)臓腑である。
風 風に当たりすぎると肝の不調が起きやすい。
目 目を酷使すると肝の不調を、また肝が弱ると目に不調が出る。
筋 肝の働きが弱ると筋肉が硬くなりやすい。
酸 酸味を少し摂ると肝を補える、逆に摂りすぎると不調をきたす。
涙 肝の不調によって涙が出やすくなる。
怒 肝が弱るとイライラ(子供は癇癪)しやすい。
青 イライラすると青筋が出る。
春は自然界のように、人間ものびのびと過ごしたくなるもの。
それができないとイライラしたり目や筋、爪(東洋医学では爪は筋の余りと考えます)など体の不調が起きたりすると考えます。
また、肝・脾・腎は血と関係が深いため生理や婦人科疾患(生理不順など)にも影響します。
植物は芽が出始め、動物は繁殖を始める春。
動き出したくなるのも自然なことですが、無理もしがちなのでほどほどを心がけたい。
不調の芽も出やすくなる時期なので、冬から春にかけての不摂生には特に注意です。
全ての時期に言えますが、その時期の過ごし方によって、次の季節がどう過ごせるかが決まってきます。
季節の変わり目にメンテナンスしておくことがおすすめです。
お読みいただきありがとうございました!