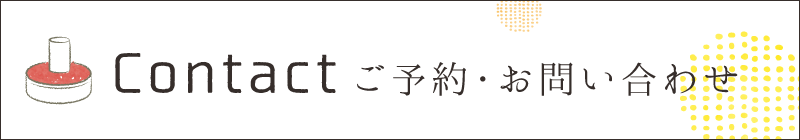体を温める②「食事編」
投稿日:2023年10月27日

こんにちは!
はりきゅうPOKKEの佐藤です。
いつもありがとうございます。
体を温めるシリーズ②「食事編」です!
うっかりボリューミーになってしまいました。。。
生活編の中でも出てきましたが、
「朝ごはんにお味噌汁」はすごくおすすめで、よく患者様にお伝えしています。
朝イチに白湯を飲んだり、お味噌汁をいただく。
なぜか?
体の中から「内臓を温める」ことができるから。
そうすると、胃腸も良く動くので(血流が良い状態)、消化吸収がうまく働き便も出やすくなります。
食べ過ぎは消化吸収にエネルギーが必要なため胃腸の負担になり、眠れなかったりだるくなったり頭がぼーっとしたりします。
本来人間の体は汗をかいたり体温を一定に保つことができます(恒温動物)。
ただ、冷たいものを多く摂取したり体を冷やしすぎたり、強いストレス(または長期間のストレス)がかかって血流が悪くなると、消化不良、便秘、内臓の不調、体のこりや痛みが出てきます。
なので夏も冬も関係なく、内臓の冷え対策は大切。
さて、ここでは東洋医学的な視点からみた「食」についてご紹介します。
冷えない体を作る、という意味で参考になればと思います。
栄養バランスなどは厚生労働省のホームページなどで紹介しているのでご参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html
東洋医学的な栄養バランス
栄養素のバランスは、5行で考えることもできます^^
以前5行については書いたことがありますが、
https://pokke89.com/blog/3821/
食べ物や食べ方も「5つ」に分類できます。
色、味覚、穀物も分類できますのでご紹介していきます。
東洋医学ではほとんどのことを5つに分類します。
人の体質も5つに当てはめることができたり、体の場所、働き、季節や時間帯、食べ物の味や性質、匂いまでなんでも分類していくことができます。

↑手作りしました5行(食に関するものの一部)の図。
解説していくと、
木・火・土・金・水とは、自然界での一連の流れを表しています。
木が燃えて⇨火になり⇨火が消えて(灰)土になり⇨土の中から金(鉱物)ができ⇨金属から水が滴る⇨水が豊富だと木が育つ・・・というふうに巡っている。
これを「相生」と言います。
また、向かい合う関係では(星型に)「相剋」と言ってお互いに抑制し合う性質があります。
それぞれのバランスが保たれていることが理想で、本来体は無意識にそれを保とうとしています。(ホメオスタシスと同じようなこと)
では一つづつ解説です。
季節ごと&体質別と捉えてください
「春」 「肝タイプ」
こんな方におすすめ
春に体調を崩しやすい、イライラ、気分の落ち込み、目の不調、爪が弱い、貧血
葉物野菜、春にとれる山菜など旬のもの。
少しの酸味をとると良い。
穀物は麦。(真っ白ふわふわなパンではなく全粒粉など穀物の味のするものが体を温めます)
・・・だから女性はパンが好きなのでしょうか?
「夏」 「心タイプ」
夏に体調を崩しやすい、顔が赤くなりやすい、高血圧、緊張しやすい
赤い食べ物、トマトや赤パプリカなど 夏の野菜(しかし夜に生野菜は体を冷やします)
黍(きび)とはとうきび(とうもろこし)などのこと。
汗が出すぎる、感情が昂りやすい場合などは、腎による抑える力が弱いこともあります。
その場合は「腎」を補うことも大切です。
「土用」(梅雨や各季節の土用) 「脾タイプ」
梅雨の時期に不調、胃腸が弱い、体が重い、肌荒れ、気持ちが落ち込む
黄色や甘みを感じる食べ物。カボチャ、芋など。
粟(あわ)はメジャーではありませんが「五穀」のひとつ。
甘みと言ってもコンビニスイーツなどに使われる上白糖(三温糖も)は体を冷やすため、きび砂糖や黒糖を使ったものがおすすめ。
「秋」 「肺」
秋に体調を崩しやすい、肌の乾燥、喉が弱い、鼻炎、喘息など
稲(米)(玄米でも白米でも美味しいと感じる方で)。
薬味として「辛」いものを少し。
大根やかぶなどの根菜を摂る。(スープや煮物で温かく)
体を中から温め呼吸器系の不調を予防できたり、治癒を早めたくれたりします。
「冬」 「腎タイプ」
冬に体調を崩しやすい、冷え性、高齢者、不妊、膀胱炎になりやすい、体力がない
小豆や大豆などの豆。
鹹(塩辛いもの)を少し。
黒豆や黒胡麻、昆布、キクラゲなども良い。
昔から言われている
ま(豆)ご(ゴマ)わ(わかめ)や(野菜)さ(魚)し(椎茸・きのこ)い(いも)
とちらもとても大事ですね。
そしてお酒を飲む人はいいお酒を嗜む程度で。
四季のある日本では、昔からその季節の旬を頂きながらシンプルに養生できていたんですね。
何事もバランスよく。(できない時ももちろんありますが^^;)
こういった知識があると、食材選びや献立に役立つかと思います。
自分に合っているのはどんな食生活か、
知識を持って無駄なく楽しく温活してください^^
長くなりましたが、
お読みいただきありがとうございました!
次回は③「服装編」です。